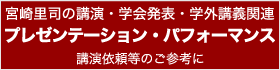タスク集『Project M』作成資料
はじめに
言語習得に成功した人々の共通点を調べると,身近にある生のリソース(テレビ,インターネット,人とのネットワークなど)を利用し,自分なりの学習方法を工夫している人が圧倒的に多い。
つまり,成功のポイントは教室場面の勉強だけでなく,教師の管理から離れたところでどのように学習するかということによるところが大きい。
言い換えれば自分にあった自律的学習を身につけ,自分の学習を自分で管理することが成功のカギなのだ。
本書は早稲田大学日本語教育センターにおける日本語教育研究講座で宮崎里司担当の「言語学習ストラテジー概論」の受講生が作成したタスク集です。
講座の受講生は現役の大学生,大学院生の他,留学生,日本語教師,英語教師,ボランティア講師などがおり,それぞれ違った立場から「効果的な言語習得とはなにか」をテーマに研究してきました。
まず第1段階としてKristine BrownのMonitoring Learner Progress.の翻訳を試みることで,「学習過程をモニターすること」の意味について学習しました。
原書はオーストラリアの成人の英語教育に関する研究プロジェクトの一環として書かれたもので,研究,理論,実践を総合化させながら,学習において進歩を続けていくためには「学習過程をモニターすること」が重要であると説き,モニターの方法につきさまざまな角度から提案がなされています。
学習者自身の自律学習を促しながら学習者の習得過程をモニターするストラテジーを教師が身につけることは,教室での活動にも大いに役立つと思われます。
次に学習者へのインタビューをすることで,学習者の学習体験や学習上の問題点,工夫点を集め,タスクづくりの参考としました。
1年の総まとめとして,授業を通して私達が強く感じた「自律学習の大切さ」を外国語学習にかかわる方々に発信したいと,ストラテジートレーニング用のタスク作成というプロジェクトにとりくみました。
タイトルの『PROJECT M』は指導した担当者宮崎の「M」,そしてモニター(Monitor)の「M」を意味しています。
本書に掲載したタスクはまだ試作段階で完成品とは考えておりませんが,言語学習にかかわる方々が自律学習を意識するきっかけとなり,今後の学習活動のお役にたてれば幸いです。
受講生一同
本書の特徴
目的
本書で紹介しているタスクは,学習ストラテジーのトレーニングを目的としています。学習ストラテジーの分類については様々な専門書が出ているので,ここでの解説は割愛しますが,本書では,Oxfordが定義する六つのストラテジー(「表1」参照)に基づき,各タスクが,どのストラテジー習得を目指して作成されたかを明確に提示しました。
| 直接ストラテジー | 記憶ストラテジー |
|
| 認知ストラテジー |
|
|
| 補償ストラテジー |
|
|
| 間接ストラテジー | メタ認知ストラテジー |
|
| 情意ストラテジー |
|
|
| 社会的ストラテジー |
|
また,特に以下の2点に着目して,タスクを考えました。
1. 自律学習を促進する「ネットワーク作り」
自律学習の継続のために,学習計画を立て,学習をモニター・評価する,ネイティブとのネットワークを作り,交流を図る,といったストラテジーが不可欠であり,これらの「間接ストラテジー」に関するタスクを数多く紹介しています。
中でも,言語習得においてインターアクションは欠かせない要素であるため,「ネットワーク作り」が非常に重要であると考えられますが,この「ネットワーク作り」に悩む学習者が少なくありません。
そこで,学習者がネットワークを作るためのヒントとなるタスク,また,教室活動を通して,教師がネットワークを作る機会を学習者に提供するタスクを考えました。
2. さまざまなリソースの提案
成功した学習者は,いろいろなリソースを利用しています。本書でも,いくつか身近で学習者の動機付けとなるリソースを挙げました。教室活動用に作られた教材だけではなく,教室を離れたところで,生のリソースに触れ,それを学習に取り入れることにより,自律学習が促進すると考えられます。
構成と利用方法
- 学習者が個人で行うタスク,また,教師が教室活動を通して行うタスクに分けて掲載しています。
- 各タスクの対象となる,「学習ストラテジー」,「レベル(初級~上級)」,「場面(国内・海外)」を明記してありますので,それぞれの状況に合わせて,興味のあるタスクを選択できます。
- 日本語学習者に行ったインタビューの結果と,タスク作りの参考にした,Kristine BrownのMonitoring Learner Progress.の翻訳を掲載しました。教師はタスクを行なう前にお読みになることをお勧めします。
学習者へのインタビュー
「ストラテジー・トレーニングのタスクづくり」の手がかりを探るために,現在外国語を学習している人達へのインタビューを試みた。
インタビューは,「学習者が学習上抱えている問題」と「その問題に対してどのような解決策(ストラテジー)を見出しているか」を知ることを主目的とした。
しかし,インタビューを行った私達自身に「インタビューの過程そのもの」が「ストラテジートレーニング」になるのではないかという「気づき」のあるものになった。
インタビューの内容は,次のようなものである。
- インタビュー実施者
- 早稲田大学学生,日本語学校教師,ボランティア教室講師,日本語教師
- インタビュー対象者
- ビジネスマン,留学生,日本語学校生,ボランティア教室生徒,初級,中級,上級 計12名
- インタビューの内容
- 外国語学習の目的は何か
- 今までどのような学習をしてきたか
- 外国語を学習する上で現在抱えている問題点は何か
- 問題解決のために何かしているのか,もしあればどんなことか
- 自分なりに工夫している勉強方法はあるか
- 帰国後,どのような方法で学習を続けようと思うか
回答のまとめ
1. 学習目的
- 留学生 : 自分の専攻(日本文学,日本史,日本美術史)に活かすため
- 日本語学校学生 : 日本での進学のため
- ビジネスマン : 仕事で使うため,日本で生活するため
など
2. これまでの学習方法
- 留学生 :自国の学校で学習,留学,独学
- 日本語学校学生 :日本語の塾,日本語学校
- ビジネスマン :ビジネス場面での失敗の繰り返し,日々の生活に不可欠
3. 現在抱えている問題点
- 初級
- 地域に日本人の知り合いがいない
- 文法はわかるが,聞いたり話したりができない
- 漢字がわからない
- 学校以外で日本語を使う機会がない
- 中級
- 日本人の友達ができない
- 相手の言っていることはわかるが,自信がなくて答えられない
- 敬語がわからない
- 学校以外で日本語を使う機会がない
- 上級
- 日本人対象の講義のノートが取れない
- 若者言葉がわからない
- 間違いを直してもらえない
- 上達が実感できない
- ことわざ,格言を使いこなせない
4. 問題解決方法
- 初級
- 何もしていない
- テープを聞く
- 授業の復習をする
- 中級
- 何もしていない
- 授業の復習をする
- 日本語で話す機会を作る
- 上級
- 学校以外でも日本語で話す機会を多く作る
- 地域の教室に参加する
- わからない言葉はそのままにしないでその場ですぐに聞く
- アルバイトをして,職場で若者言葉を教えてもらう
- わからないことは日本人の友達に聞く
5. 自分で工夫している勉強方法
- 初級
- 母国語で書いてある文法書を読む
- 学校で習った言葉をすぐに使ってみる
- 毎日テープを聴く
- 中級
- サークル活動,アルバイトをする
- スケジュール表を日本語で書く
- 上級
- あらゆる生の日本語に触れるようにしている
- 好きな映画を日本語の字幕付きで見る
- イベントの企画をする
- 失敗や恥をかくことを恐れず,実際場面で外国語をどんどん使って経験を積む
- わからなかった言葉を書き留めるために小さなノートをいつも持ち歩いて記録している
- PCのホームページで友達を見つける
- インターネットで日本人とチャットで会話する
6. 母国に戻ってからの学習方法
- パソコンを活用する(インターネット,メール)
- 母国に日本の工場があるので,日本人と積極的に交流する
- 日本料理店でアルバイトをする
- 日本のテレビ,映画を見る
- まだ考えていない
インタビューから考えたこと
学習動機の意識化と上達の関係
何のために外国語を学習しているのか,外国語を使って何をしたいのか
この問いに対し即答した学習者と,質問されてからしばらく考えている学習者とに分かれた。
即答できた学習者は学習動機が学習の基盤になっていることがわかる。
なかでも「仕事のため,生活のために不可欠」と即答した学習者にとっては,外国語の上達がそのまま仕事面や生活面の向上へと結びついていく。「待った無し」の学習動機が,外国語の上達に反映された例と言えるだろう。
一方,即答できなかった学習者の中には,自らの学習動機を意識せず,ただ毎日学校へ通っていれば自動的に外国語が上達する,と考えている学習者もいるのではないだろうか。
もし,このような学習者が自分の学習を振りかえり学習動機を意識化できれば,彼らの学習になんらかの変化が現れるのではないか,と考える。
問題の意識化と解決策への模索
初級・中級レベルの学習者には,学習上の問題を意識しながらも「何もしていない,どうしたら良いのかわからない」など,問題解決への具体的な第1歩を踏み出せていない学習者が多い。
また上級レベルの学習者ほど,問題を意識し,自分なりの学習方法を工夫しているが,「上達が実感できない」など上級者特有の悩みを持っていることもわかった。
学習上の問題点を意識化できても,それを具体的な解決策へと結び付けられない学習者に対して,彼らが自ら解決策を見出し,問題解決への具体的な第1歩を踏み出せるようにするにはどのようにしたらいいのだろうかと考えた。
ストラテジートレーニングへ向けて
私達は,学習者へのインタビューを行っていくうちに,「インタビューをしたり,インタビューに答えること」で学習動機が明確化され,自分の学習方法を振りかえることができると感じた。
私達は教育をする立場であると同時に,英語やスペイン語などを学ぶ学習者の立場でもあり,私達もまた学習者と同じような問題を抱え,外国語の上達に不安を持っている。
今回優れた学習者が彼らなりに学習方法を工夫し,自ら解決策を見出していることを知り得たことは貴重な経験になった。
そこで次のような提案をしたいと思う。
教師の皆さんへ
学習者にインタビューをしてみましょう
日常の教室場面では仕事に追われ,生徒1人1人の学習目的や抱えている問題点などを把握する機会は少ないのではないでしょうか。
「インタビュー」をしてみることで,個々の学習者に対する認識を深めることができ,より効果的なバックアップの方法が見つかると思います。
学習者の皆さんへ
自分にインタビューしてみましょう
自分の学習の目的,学習上の問題点,その問題解決の方法を意識化することで,学習目標が明確となり,自分に合った効果的な学習方法を見つけられると思います。
友達にもインタビューしてみましょう
自分なりのインタビューシートを作って,あなたの周りにいる優秀な外国語学習者にイ ンタビューしてみましょう。
すぐれた学習者は自分で工夫している学習方法がきっとあります。インタビューしてみて参考になる学習方法を取り入れてみましょう。
| インタビューシート |
|---|
|
学習ストラテジー・トレーニング用タスク
| No. | タイトル | 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 言語学習日記 | 個人 | 中・上級 | 国内・海外 | メタ認知 |
| 2 | 発掘!あるある学習項目! | 個人 | 中・上級 | 国内 | 認知・記憶 |
| 3 | 書く→自信→話す | 個人 | 学生 | 国内・海外 | メタ認知・情意 |
| 4 | オリジナル日本語表現集を作ろう | 個人 | 初級~ | 国内 | 認知・メタ認知 |
| 5 | いろいろ計画をたてよう | 個人 | 学習者全般 | 国内・海外 | メタ認知 |
| 6 | ビジネス語学日誌 | 個人 | ビジネスマン | 国内・海外 | メタ認知 |
| 7 | 「リーディング・チュー太」で日本語を読もう | 個人 | 上級 | 国内・海外 | メタ認知 |
| 8 | 自分の意見をまとめよう | 個人 | 中級以上 | 国内・海外 | メタ認知・社会的 |
| 9 | ウィンドウショッピングで自分の語学力を試そう | 個人・グループ | 中級以上 | 国内 | 補償・情意 |
| 10 | キャッチコピーを作ろう | 個人・グループ | 学習者全般 | 国内 | 認知・メタ認知 |
| 11 | 自分の国と日本の衣・食・酒の文化の同・異点を調べてみよう | 個人・グループ | 日本語学習者 | 海外 | 情意・社会的 |
| 12 | みんなですき焼きパーティ・日本料理を食べに行こう | 個人・グループ | 学習者全般 | 海外 | 社会的 |
| 13 | 日本を探そう | 個人・グループ | 学習者全般 | 海外 | 社会的 |
| 14 | 地域にネットワークを広げよう | 個人・グループ | 学習者全般 | 国内 | 社会的 |
| 15 | 自国の文化を紹介しよう | 個人・グループ | 中級以上 | 国内 | メタ認知・社会的 |
| 16 | フリーマーケットに出店しよう | グループ | 中級以上 | 国内 | メタ認知・社会的 |
| 17 | 黒板カルタとり | クラス | 初級~ | 国内・海外 | 記憶・メタ認知 |
| 18 | 私がちょっとできること・・・ | クラス | 初級~ | 国内・海外 | メタ認知・社会的 |
| 19 | オリジナル日めくりカレンダーを作ろう | クラス | 初級~ | 国内 | 記憶・認知 |
| 20 | いっしょに作文を書こう | クラス | 留学生 | 国内 | 情意 |
| 21 | 申し込み制テスト~文集作成 | クラス | 初級~ | 国内 | メタ認知・社会的 |
1 言語学習日記(Language Learning Diaries)を書く
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 中・上級 | 国内・海外 | メタ認知ストラテジー |
教師の皆さんへ
言語学習日記とは,学習者が学習過程で起きる問題などを,学習日記を通してモニターするもので,学習者がどのように自己評価しているかなどを分析するための研究データとして援用される場合もある。言語学習日記には,学習者自らが書き,読み手が存在しないものもあるが,教師,ティーチング・アシスタント,ボランティアなどといった母語話者が読み手となり,コメントを書き添えながら,学習をサポートしていく方法を採用すると,長く継続できるといわれている。また,授業が学生にどう受け止められているかというフィードバックが返ってくるということは,教師の側の授業改善にもつながり,学習活動の工夫や学習者の要望への対応など,学習者側に視点をおいた授業への構えを教師に意識づけることにもなる。日記という形態であるため,学習者が広い範囲のテーマや問題をカバーしがちになった場合,的確な学習過程へのコメントなどがしにくくなることがあるため,慣れていない学習者には,事前に書き方のフォーマットを提供したほうがよい。
学習者の皆さんへ
学習者が自己反省・自己評価を行うことによって自分自身をみつめ,学習の改善をはかる手助けになるばかりでなく,個々に自律学習への意識づけをし,学習者の学習態度や意欲の向上にもつながるものです。受け身的な学習から,少しずつ自分の学習に対する視点を変えてみましょう。下に言語学習日記のサンプルを示しておきます。これは,早稲田大学大学院日本語教育研究科で学ぶ中国からの留学生が書いた1週間分の学習日記です。少し長いですが,どのように自分の学習プロセスをモニターしているかを,読み取ってみましょう。
- タスク1(個人)
- 12月5日の日記を読んで,Sさんが,自分の日本語についてモニターしているところを探してください。次に,それぞれのモニターの箇所で,Sさんは,どのような問題がありましたか。
- タスク2(個人)
- Sさんは,12月5日から11日まで,いくつぐらい日本語についてのモニターを行いましたか
- タスク3(個人)
- Sさんの日記の中で,文法,表記などの誤りがあれば,選び出してください。
- タスク4(個人)
- あなたのモニターとSさんとは,どんなところが違いますか。考えてみましょう。
- タスク5(ペアまたはグループ)
- 言語学習日記以外の,効果的なモニターの方法を考えてみましょう
例
早稲田大学日本語教育研究科 修士課程1年 留学生Sさんの言語学習日記(2001年12月5日-11日)[PDF: 47kb]
2. 発掘!あるある学習項目!
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 中・上級 | 国内 | 認知・記憶ストラテジー |
目的
「授業でやった事が実生活で使われない。」という声を聞くが,活用すべき時にできていない事も多い。
特に補償ストラテジーに長けた中上級者であると,学習中の複雑な構文や項目をあえて使わずともある程度の意思疎通ができるようになる為,学習事項を使う適切な場面を見つけて意識的に使っていく事が上達のカギとなる。
そこで次の授業までに学習した項目を日常場面でできるだけ見つけ出し,それを具体的に活用することで,学習内容を定着させていく事がこのタスクのねらいである。
方法
- 授業内での学習項目(語彙,文法,文型)をなるべく多くノートに書き込む。
- 項目を常に意識(見直す,思い返す)しながら日常生活でチェックする。
- 項目を使ったり,使われた場面に出会ったら,その使用法を書き留める。
- 常に意識して使えるようになるまで続ける。
発掘ノート(記入例)
| 項目 | 使った場面 | 使われた場面 |
|---|---|---|
| 自動詞 | 駅のホーム あ,財布がおちましたよ |
スーパーマーケット フランスパンが焼きあがりました。 |
| 受身 | . | 新聞記事ATMがまた壊された |
| ・・てしまう(完了) | 今度こそ宿題を早めに終わらせてしまおう。 | . |
| ・・てしまう(後悔) | ポケットに千円札をいれたまま洗濯しちゃった。 | . |
| ~と言いました。 | . | ニュース小泉首相は「解散は全く考えていない」と述べました。 |
| ~たり,~たり | ジュースを飲んだり,お菓子を食べたりしました。 | . |
3. 書く→自信→話す
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 学 生 | 国内(海外) | メタ認知・情意ストラテジー |
目的
日本に留学にきている学生の強みはなんといっても一歩外に出れば,そこは日本語が当たり前に使われている状況である,ということである。せっかく日本に留学にきたのなら,その状況を利用しない手はない。しかし,まだ来日したばかりであったり,自分の日本語に自信が持てなかったり,日本には友達がいないなどの理由で毎日が学校と家,バイト先の往復になっている学生も多いのではないだろうか。そこで「もっと外へ出てネットワークを作ろうとしなければだめだ」とアドバイスをするのは簡単だがここではそれに到るまでのステップとしてこのタスクを紹介しようと思う。
まず,日記に自分の言いたいこと,思ったことなどを書き出して,それを自分で間違いを正すことで自分の意見を整理し,それを教師やその他の日本人,場合によっては同じ日本語学習者に対して口に出していくことで日本語を話すことに慣れようというのがこのトレーニングの目的である。
活動内容
- まず,どのくらいの頻度で日記を書くかを決める。毎日書くことが望ましいがアルバイトや授業などに支障が出たりすると続かないのであまり重荷にならない程度がよい。また,週に二回書くと決めてそれが達成できなくても諦めてしまうのではなく続けていくことが重要である。
- 実際に日記を書いてみる。日記を書くことに慣れている人はどこへ行った,何をしたということだけではなく,その場面で感じたことも書いておくとよい。できるだけ人に伝えることを前提とした内容や文体を意識する。授業で習ったことを使うと理解も早い。(せっかく日本にきているのなら自分の行きたいところに行ってみるとよい。その方が思い出などもあって日記も書きやすい。)
- 読み返してみて間違っていたり自身のない部分を辞書や教科書を使って確かめ,直す。自信のないところ以外は,いちいち辞書を調べるのは労力が無駄にかかり日記を続ける妨げになるのでしないほうがよい。むしろ話すときに使ってみて間違いを正してもらったほうが勉強になる。
- 実際に話す場面で使ってみる。使う場所はどこでもいいが最初は教室場面や授業の前や後など教師に間違いを正してもらえるところがよい。慣れてきたら友達の日本語学習者同士の間で使ってみるのもよい。話すときに書いたものは見ながら言わないようにする。
- 使ってみて見違いを指摘されたところやよりよい表現を発見したところは,日記に書き込んでおく。
なお,このトレーニングは日本を離れ母国に帰ってからでも,話す場と直してくれる人がいればできる。また,慣れてくれば直してくれる人は必要なくなるかもしれないが,日記を書くことだけになってしまわぬよう誰かに話す,あるいはメールなどでもいいので自分以外の人に伝えられることが大切である。
4. オリジナル日本語表現集を作ろう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 初級~ | 国内 | 認知・メタ認知ストラテジー |
目的
- 日常生活の中で日本語の言い回しや単語を学ぶ。
- 新たに覚えた日本語を記録し,自分自身の学習に役立つテキストをつくる。
活動のねらい
日本語学習者は毎日の生活の中で,「言いたいことはあるのだけれどなんと言ったらよいのかわからない。」「この単語は日本語でなんと言うのだろう。」「この日本語はどういう意味だろう。」と考えてしまうことがよくある。 電車の中やテレビ,映画などで耳にした新しい日本語,新聞や雑誌,あるいは町中で目にした知らない日本語などの意味や使い方を,話している相手や周囲の人にその場で聞いたり,後で先生や日本人の友達に教えてもらったり,辞書で調べたりしながらシートにどんどん記録し,独自の日本語表現集を作るのがこのタスクである。 書くことで表現が自分の中で定着するし,あとで調べるときにも役立つ。いつ,どんなところで覚えたかを記録しておくのも参考になる。
タスクシート(記入例)
| 日時 | 日本語の表現 | 場所・状況 | 意味・使い方 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | 「~はご遠慮下さい」 | アルバイト先のレストランでお客さんに | してはいけないことをていねいに伝えるとき。レストランやコンビニ,電車の中や劇場など,お客さんに言うときは絶対これ。(例)「タバコはご遠慮下さい」「携帯電話の使用はご遠慮下さい」などと使う。(×)「タバコはだめです」「タバコは吸わないでください」「タバコは禁止です」は失礼だから使ってはだめ。「タバコは遠慮してください」も使わない。 |
| 9 | 「つまらないものですが・・・」 | アパートの大家さん(田舎の柿を持ってきてくれたとき) | 人にものをあげるとき,日本人はよく使う。高価なものや本人が気に入っているものでもそう言うのでホントにつまらないものだと思わないこと!決まり文句として使っている。 旅行の土産,田舎から送られてきた食べ物などをあげるときなどによく使う。 |
| 10 | もとカレ | 大学の女友達が使っていた | 別れたボーイフレンド,前の彼氏のこと。 「もとの彼氏」の省略。省略語は最近特に若い人がよく使う。例「デパ地下」「早弁」「だめもと」 |
| 18 | ・・・つーか | 電車の中の男子高校生 | 「・・・と言うか」の若者ことば。「というよりむしろ」「別の言い方をすれば」「そういう意味じゃなくて~」などの意味。*携帯電話の「ツーカー」はこれとは関係ない。 |
5. いろいろ計画をたてよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 学習者全般 | 国内・海外 | メタ認知ストラテジー |
目的
何か始めようと思ってもなかなか長続きしない学習者の皆さん。始める前にちょっと考えてください。何のためにするのか。どんな方法でするのか。そこで計画を立てて目標に向かって少しずつ努力をしましょう。
急に計画を立てようといっても立てられませんね。大きいことから少しずつ計画をすることで日常の小さなことも計画を立てられるようにしましょう。
ではstep1から順番にやってみましょう。
step1 タイトル:「人生設計をしよう」
「あなたのこれからの人生を大きく三つの段階に分けて考えてみましょう」
例)
|
|
|
step2 タイトル:「日本語学習の計画をしよう」
期間: 月~ 月,目標レベル:(初級/中級/上級)
| 月から 月まで |
| 目標: |
すること:
|
step3 タイトル:「今月の学習計画をしよう」
| 月から 月まで |
| 目標: |
すること: |
step4 タイトル:「今週の学習計画をしよう」
| 月から 月まで |
| 目標: |
すること: |
step5「カレンダーに◎○△をつけよう」
学習目標がとてもよくできた日には◎,まあまあの日には○,あまりできなかった日には△をつけましょう。毎日◎がつくようにがんばりましょう。
△をつけた日はどうして△をつけたか考えましょう。
- 目標が難しすぎたのかな?
- 何をしなかったのかな?
次は気をつけましょう。同じ失敗はしないようにしましょう。
6. ビジネス語学日誌をつけよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | ビジネスマン | 国内・海外 | メタ認知ストラテジー |
目的
仕事で外国語を使用しているビジネスマンは日々の業務に追われ,ある程度の語学スキルが身についた後は,ブラッシュアップの必要性を漠然と認識していながらも,
- 日々どのようなビジネス場面で外国語を使用し,自分のレベルがどの程度なのか
- どういう点が改善されるべきなのか
について客観的にモニターする機会も意識もないのではないだろうか。
食事の接待や観光地へのアテンドなどの際には単なる語学能力だけでなく,話題の豊富さもビジネスマンにとっては大事な要素となる。そのためには平素から日常生活の中でさまざまな題材をみつけだし,それを外国語でまとめる訓練や,話題を増やすための情報収集も必要となる。
出張時,駐在時は母国での業務より時間にゆとりが持てるケースが多く,ビジネス場面以外で外国語に触れる機会がぐっと増えるので,ある期間ビジネス語学日誌をつけてみて,仕事面,生活面での自分の語学能力を記録,分析してみてはどうだろうか。
ビジネス語学日誌
月 日
| 仕事内容 | 話す | 聞く | 書く | 読む | 評価・ 反省 |
|---|---|---|---|---|---|
| (現地)顧客,役所,銀行とのミーティング | △ | ○ | . | . | 確認すべき事項がもれてしまった |
| 議事録作成 | . | . | △ | . | 要点をまとめる能力を磨く必要あり |
| 契約書作成 | . | . | ○ | ○ | 契約書特有の文書構成,言い回しはもう大丈夫 |
| 電話による折衝,確認 | ○ | . | . | . | . |
| ACTIVITY | 話す | 聞く | 書く | 読む | |
|---|---|---|---|---|---|
| レストランで頼んだものと違うものが出てきた。 | X | . | . | . | 仕方なく,そのまま食べた。 |
| ホテルの部屋でハリーポッターを(外国語で)読む | . | . | . | ○ | . |
| . | . | . | . | . | . |
今日の反省点,言えなくて困ったことなど
|
新しく覚えた表現,その他知り合いになった人や新しく行ったレストランの情報など
|
7. 「リーディング・チュウ太」で日本語を読もう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 上級 | 国内・海外 | メタ認知ストラテジー |
「リーディング・チュウ太」とは
読解学習支援システムで,辞書機能(「日日」「日英」「日独」)と語彙チェッカー機能(文中の単語が,日本語能力試験の何級に当たるか)を持つ。
オリジナルの語彙リストを作成することも可能。
http://language.tiu.ac.jp/index.html
タスク内容
初級レベルの学習者に比べ,上級レベルの学習者は,上達のスピードが遅くなるため,伸び悩む場合が多い。
「リーディング・チュウ太」を使い,生の日本語を読み,自分のレベルをチェックすることで,自分がどのくらい上達したかを客観的にモニター・評価することができる。
手順
- WEB上で,興味のある文章を探し,読む。
- その文章を「リーディング・チュウ太」に貼り付け,意味の分からない単語を調べ,精読する。
- 語彙チェッカー機能を使い,分からなかった単語の難易度を調べることにより,自分のレベルを把握することができる。
8 自分の意見をまとめよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人 | 中級以上 | 国内・海外 | メタ認知・社会的ストラテジー |
目的
新聞記事を読んで興味を持った記事について作文を書き,読解力および作文の力を自分自身で評価する。(スキル:読む,書く)
活動のねらい
学習者は日本語の新聞をどれくらい読んでいるだろうか。 新聞は日本語学習の身近なリソースとして様々に使えるが,学習者はそれをどれくらい理解できるのだろうか。 新聞を読み,興味を持った記事について感想や意見を書き,読解や作文の力をモニターするのがこのタスクのねらいである。 また,書いたものを先生や友達に読んでもらったり,意見を求めたりしながら他からの評価も得る。 また,新聞には投稿欄など読者の意見を求めるページもたくさんあるので書いたものを新聞に投稿して未知の読者に読んでもらうのも励みになると思われる。 特に外国人の意見を掲載するコーナーなどをもうけている新聞はたくさんあるので利用するとよい。また,母国に帰ってからもインターネットなどを使えば日本の新聞を簡単に読むことができ,投稿も可能なので帰国後も続けると効果的である。
タスクシート
- 新聞を読んで興味を持った記事の中からひとつ選ぶ。(できれば「特集」などで読者の意見が求められているものがよい。)
- 選んだ記事について感想や意見をまとめる。(あまり長くなくてもよい。自分の考えがはっきりわかるように書く。)
- 先生や友達など,書いたものを読んでくれる人がいれば,読んでもらい,意見やアドバイスを聞く。
- 書いたものを新聞社に投稿する。
| 日付 |
| 記事の内容の要約(記事を切り取って貼り付けてもよい) |
| あなたの感想・意見 |
参考資料(以下,新聞社の投稿先をいくつか掲載しておくので参考にされたい)
【郵送による投稿】
- 朝日新聞「声」
- 〒104-8661 東京京橋郵便局 私書箱300号 朝日新聞「声」係
- 毎日新聞「みんなの広場」
- 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞東京本社「みんなの広場」係
- 読売新聞「気流」
- 〒100-8691 東京中央郵便局 私書箱325号 読売新聞「気流」係
【メールによる投稿】
- 読売新聞:webmaster@yomiuri.co.jp
- 朝日新聞:kouhou@mx.asahi-np.co.jp
- 毎日新聞:webmaster@mainichi.co.jp
- 産経新聞:opinion@sankei-net.co.jp
- 日経新聞:webmaster@nikkei.co.jp
- 東京新聞:webmaster@tokyo-np.co.jp
【その他】
- 東京新聞:http://www.tokyo-np.co.jp/dokusha/
- 日系マスターズ・クラブ:http://masters.nikkeibp.co.jp/masters/contribution/ 「自由投稿」と「テーマ投稿」を受け付けている。
これ以外にも特集記事に対する意見を募集するなど様々なかたちで読者の意見を求めることがあるので,新聞にはこまめに目を通す習慣をつけるのが良いでしょう。
新聞以外にも雑誌や,地域のミニコミ誌なども利用できます。
9. ウィンドウショッピングで自分の語学力を試そう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 中級以上 | 国内 | 補償・情意ストラテジー |
対象
日本に来たものの,あまり日本人と話す機会がなく,自分の日本語力に伸び悩みを感じている中・上級の日本語学習者
ねらい
このタスクのねらいは,学習者が自分で適度のリスクを負い,なるべく自然に日本語で会話ができるようになることである。ある程度日本語が話せても,自分の語学力に自信を持つことができない学習者に必要なのは,教室場面ではなく(つまり教師のコントロールを離れて)教室外において学習者の母国語を話せない日本人と話す機会をなるべく多く持つことだと思われる。そのような機会は学習者を自然に日本語しか話せない状況に追い込むにことなり,学習者はリスク(誤解やあまり円滑に進まない会話など,コミュニケーション上の失敗の可能性)を負うことになるが,うまく会話が進んだときには自分の語学力への自信を深め,さらなる語学学習へのモチベーションを高めることができる。また,たとえ失敗したとしても悲観的にならずにその失敗を分析し,原因を突き詰めれば次の機会につながるはずである。また,このタスクを周期的に行うことによって(たとえば2週間に1回)日本語話者に話し掛けることに慣れ,学習者の語学練習のネットワークを広げるだけではなく,そのネットワークから友情が生まれればこのタスクの意義が大きなものとなるだろう。
必要な言語スキル
基本的に日常会話(自分のことを話したり世間話をするなど)ができれば問題はないだろう。ただし,会話の切り出し方(あのー・すみません,など)・会話の終わり方(じゃあ,また来ます・それじゃ,また今度,など)・話題の変え方(ところで・そういえば・実は僕/私~,など)といった決まり文句は必要だと思われる。
手順
- 学習者は自分の趣味や興味のあることを考え,それに必要な道具(例えばテニスが趣味ならラケット)が売っている店・もしくはデパートに行く。なるべく混んでいる店は避ける(言い方は悪いが店員が暇そうな店がよい)。
- 店員が話し掛けてきたら商品の説明を受けつつも,会話の節々に自分の母国のこと(母国のテニス事情)や自分自身についての情報を盛り込み,店員の興味を引く。あとはなるべく長く会話を楽しむ。
- 頃合いを見計らって帰る(商品を買ってもよいがあくまでも会話を楽しむのがこのタスクの目的である)。
- 忘れないうちに店員と話したトピック,店員が使った語彙を学習日記に書き留める。
応用
あまり決まった趣味を持たない,あるいは道具を必要としない趣味を持つ学習者は,なるべく空いている平日のデパートの洋服売り場に行けばこのタスクを行うことができる。また,一人で店に行くのが億劫な学習者は,自分とは違う母国語を話す学習者と共にこのタスクを行ってもよい。さらに,デパートに限らず,様々な店や飲食店でこのタスクを試すことができるだろう。たとえば,つり具店,ゴルフ道具屋,スキー洋品店など学習者の趣味に直結した所から,規模の小さいレストランや喫茶店など,顔を覚えられやすい所で店員に話し掛ければネットワークを作りやすいだろう。
10. キャッチコピー(広告)を作ろう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 学習者全般 | 国内 | 認知・メタ認知ストラテジー |
ねらい
電車の車内広告などに注目し,「ナマ」の日本語を感じる。効果的な日本語の使い方を知り,身近な商品のキャッチコピー(広告)を作ってみる。
※初級者は,作文でよい。上級者は,どうしたらその商品が魅力的に感じるかを考えて,キャッチコピーを作る。
方法
- 電車に乗っているとき,車内広告に注目。気づいたことを,メモする。
| 私が注目した広告(商品の種類) | 気づいたこと |
|---|---|
| 「利きそう」なのど飴より,「利く」のど飴(のど飴) | 「利きそう」よりも,「利く」の方が,インパクトを与えるらしい。 |
| 「結婚式場選びならおまかせ」(式場の斡旋) | 「おまかせ」というと,いかにも頼れそうなイメージがある。 |
| 「裸の味がする」(タバコ) | 「裸」に込められた意味は? |
| 「業界初!基本料0円」(?) | 「業界初!」が目をひく。 |
| 「寅さんだってフリーター」(大学の公開講座) | 「寅さん」=日本映画の主人公。「フリーター」=今の日本の若者の働き方のひとつ。働き方についての講座か? |
- 自分の気に入った商品を,クラスの人に売り込むべく,キャッチコピー(広告)を作る。
| 商品名 | キャッチコピー(広告) |
|---|---|
| 4色ボールペン | 「1本4役,これは便利」 「1本のボールペンで,4色使えて,便利です」 |
| 肉まん | 「あったか,いい気分」 「温かくておいしいです」 |
| 新型の携帯電話 | 「待望のニューモデル登場!」 「新型の携帯電話が出ました」 |
| 軽量傘 | 「驚きの軽さ!○○g」 「軽くて持ち歩くのが便利です」 |
11. 自分の国と日本の衣・食・酒の文化の同・異点を調べてみよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 日本語学習者 | 海外 | 情意・社会的ストラテジー |
目的
自分たちの努力で面識のないネイティブを掴み,インタビューを行い,友人関係を維持する能力の育成。
方法
大学を訪ね,日本人留学生をみつけ,自分で用意した質問シートをもとに質疑応答を行う(自分の国のことも教えてあげるー日本人の留学生にも生活上役に立つため)。
インタビューの内容
- 衣――20代のファッション
- 食――主に食べる家庭料理
- 酒――酒の文化
学習項目
- 初対面の人に対する依頼表現
- 話の切り方
- 話の進め方
- 単語の習得
- 次につなげる工夫
質問シート
| 衣について |
|---|
「最近,日本の20代に―――――――」
|
| 食について |
|
| 酒について |
|
12. みんなですき焼きパーティー・日本料理を食べに行こう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 学習者全般 | 海外 | 社会的ストラテジー |
タスクのねらい
- 日本で日本語を学習した学習者が,日本を離れて海外に居住しながら日本語を忘れないために,あるいはそれ以上の語学力を身につけるためのモチベーションアップとして利用する。
- 海外の教室活動の延長としても利用できるが,個人で身近な友人,ルームメイト,大学の日本人,近所の人達に声をかけながら,日本料理を作ったり,あるいは,おいしい日本料理の店を見つけ出し,みんなで食べに行くことで,学習した日本語を忘れず,さらには自分の日本語学習を進めていく学習の動機づけにする。
- タスク1,タスク2のシートには,それぞれの活動を進めていく一例を示した。これを利用する人は,その他各自でオリジナルのシートを作って,たくさんの情報を集め資料としてストックすることができる。
- また,これらのタスクは,海外に住む人達だけでなく,逆に,海外から日本に来て,日本語を学習している学習者やその仲間たちの学習ストラテジーのタスクとしても利用できる。
例:タスク1
自分の国の料理を作って,みんなにご馳走しよう。
例:タスク2
国の料理を食べに行こう。(日本にあるお国の料理店を探して食べに行く)
- 自分の国の料理を作り,身近な友人,大学の日本人などにご馳走し料理法なども紹介する。
- 日本語でレシピを作り,料理法を説明していくことで日本語使用の場も増え,仲間も増え,ネットワーク作りができる。
- さらに,違う国から来ている人達にも,その国の料理を紹介してもらう。次には,日本にある,その国の料理店を探してみんなで食べに行く。
- 仲間に入った日本人は,いつか本場に行ってその料理を食べたいと思うであろう。お国の料理マップを紹介してもらい,実際に友人の国に行って料理を食べよう!という話になる。
*料理を一つの手段として,いつまでもつながっていくネットワーク作りを勧めたい。
タスク1:みんなですき焼きパーティー
日本でよく食べた料理のひとつを作ってパーティーを開く。きょうは,すき焼きにする。
- リストを作る(日本でいっしょだった友人,近所の人,大学の日本人)
- ポール
- 山田さん
- 案内状を書く(もちろん,日本語で,毎日会っている人には電話する)
- 日時
- 料理名
- 会費
- 出欠
- 材料を書き出す
- 牛肉
- 豆腐
- 買い物の分担をする(買った人は,店の名前と値段を報告する)
- ポール(肉と日本酒)
- 山田(ねぎ,しいたけ,えのき)
- 料理する前に準備することをメモして,みんなに配る
- しらたきを食べやすいように,切っておく。
- 焼き豆腐,長ねぎ,他の野菜も適当な大きさに切っておく
- しいたけは,
- 料理の手順を確認する
- コンロですき焼きなべをあつくする。
- 熱くなったら,
- さあ,作りましょう
- 食べながら,日本の思い出を話す(楽しかったこと,失敗談など)
- 次のパーティーのメニューを決める。
- 日時も決める
タスク2:日本料理を食べに行こう
※日本料理のおいしくて,安い店をさがして,みんなで食べに行く。
- まず,手分けしてどこに日本料理店があるか,さがす
- 電話帳で
- 地図で
- 友人に聞く
- 電話で聞く場合のストラテジーを考える
- すみません。お店に行きたいんですが,どういったらいいですか。
- はい,地下鉄でしたらオックスフォードサーカスが一番近いです。
- 日曜日はお休みですか。
- ランチタイムは何時から何時までですか。
- みんなで分担して,報告する
- さくら (オックスフォードサーカス)
- 月曜~土曜 正午~2:30pm,5:30pm~9:30pm,日曜 正午~2:30pm,6:30p~9:30pm
- 無休
- 何人かで,下見に行って食べる。感想を書く
- さくら:おいしいが,値段が高い
- 北海(ピカデリーサーカス):ランチメニューがある。安くておいしい。
- 菊
- 店が決まったら,日時を決めてみんなに知らせる
- 日本料理店 北海
- 場所:ピカデリーサーカス 現地集合(簡単な地図を書く)
- 日時:12月20日(土) 正午集合
- 電話番号:734-5826
- 値段
- しっかり,味わい次回はみんなで作りましょう。(材料など,組み合わせを参考に)
- 店にある,他のメニューや値段をメモする
13. 日本を探そう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 学習者全般 | 海外 | 社会的ストラテジー |
目的
身の回りで日本語を使えるネットワークを探す。
タスク
あなたのまわりの日本語が使える環境を探しましょう。
| 項目 | あなたの町 | 知り合った人 | 感想 |
|---|---|---|---|
| 総領事館関係 | 在メルボルン日本国総領事館 | 宮崎さん | 緊張したが,親切な方だった。 |
| 日本食料品店 | メルボルン大丸 | . | . |
| 項目 | あなたの町 | 知り合った人 | 感想 |
|---|---|---|---|
| 総領事館関係 | . | . | . |
| 日本語メディア | . | . | . |
| 日本人会 | . | . | . |
| 日本レストラン | . | . | . |
| 日本食料品店 | . | . | . |
| 主な進出企業 | . | . | . |
| 日本人会 | . | . | . |
| 旅行代理店 | . | . | . |
| 日本人学校 | . | . | . |
参考文献
宮崎里司 2000 「もうひとつの日本事情:海外でのインターアクションのための日本語教育」『21世紀の「日本事情」』2 pp.42-51
14. 地域にネットワークを広げよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 学習者全般 | 国内 | 社会的ストラテジー |
目的
来日してまもない日本語学習者(特に日本人の配偶者となった学習者,あるいは家族の転勤で来日した学習者)は友人や知り合いも少なく,またどうやって知り合いを作れるのかさえもわからず自宅に引きこもりがちである。
家族間では母国語での会話となり日本語の上達はままならない。
また留学生,日本語学校の生徒は同じ国から来日した生徒同士がかたまって生活していることが多く,日本にいても母国語での会話が中心となりこれもまた日本語上達の妨げとなりやすい。
そこでまず地域の国際交流協会にアクセスすることで,地域社会へ第一歩をふみだし,「自分にとっての地域とのかかわり方」を模索しながら,人とのネットワークを広げていく方法を提案したい。
はじめは周りの人に助けてもらうことが多いかもしれないが次第に「地域に対して自分が役にたてること」に目をむけ地域社会の中での自分のポジションを確立していって欲しい。その経験は日本で生活する上で大きな自信となり,自分自身で広げていったネットワークは大きな財産となる。
国際交流協会のホームページの活用法
- 多言語訳語情報を有効に利用しよう
- 国際交流のサイトは,ほとんどのサイトでEnglish versionが用意されているし,多言語対応サイトも増えている。そのサイトにアクセスすることにより,地域で生活するうえで必要となる情報を引き出そう。
- 初級者は母国語と日本語を比べながら,生活上必要な日本語の語彙を覚えよう。
- 中級~上級学習者は母国語version と日本語version の文章をくらべることで,ホームページそのものが「生きた教材」となる。
- 引き出せる情報の例
- 各種登録手続き
- 教育,福祉
- 保健,医療(多言語医療問診票など)
- 緊急時情報
- (*パソコンを持っていない学習者は,外国人向けの区報,市報を入手する)
- 日本語学習支援団体を利用しよう。
- 地域のボランティア教室では個々のレベルに合わせて日本語学習支援をしている他,クリスマス会,ピクニックなどさまざまな行事を通して,講師と学習者,学習者同士の親睦を図っている。ボランティア教室にはさまざまな国から生徒が集まっている為友達もできやすく,学習や行事を通して学習者同士がお互いに支えあう場となっている。
- 伝統文化教室に参加しよう
- 交流協会によっては生け花,琴などの日本文化教室,外国人講師による外国の文化紹介教室を主催している。
- この種の教室に参加することで,日本文化や他国の文化に知識を深められると共に人間関係のネットワークを広げることができる。興味を持ったものについてさらに知識を深める過程で日本語も確実に上達していく。
- 各国料理教室に参加しよう
- 日本人や外国人が講師となり,日本料理やお国料理を紹介する講座が各地で開かれている。
- まずは日本料理の講習会に参加し,作り方を覚えるとよい。
- 日本語のレシピを読むことは日本語の勉強になる。次にマーケットやレストランに行き食材の日本名をおぼえていく。
- 何回か参加することで日本料理のレパートリーを増やすことができ日本での食生活をゆたかにすることができる。日本の料理番組をみてみるのもよい。
- 次に各国料理の講習会に参加し,今度は他の日本語学習者がどのようにレシピを書いているかに着目・観察し,料理の本をみながら自分の国の料理の日本語版レシピづくりをイメージしはじめる。何回か料理教室に通うことで友人もでき,料理以外のさまざまな情報交換ができる。
- さまざまなイベントへの挑戦~参加者から主催者へ~
- 地域で開催されるイベントに参加することは日ごろの日本語学習のまたとないOUTPUTの場になる。
- 各国文化紹介,各国料理教室講師への挑戦
- 日本語スピーチコンテスト出場
- 月刊情報誌の「お国自慢大募集」などのコーナーへの投稿
- 国際交流のつどいにボランティアとして参加
- 企画,運営,当日の手伝い
- 発表にむけた準備作業と,ひとつのことをやり遂げた自信は日本語学習面,生活面に大きな成果をもたらすと確信する。
15. 自国の文化を紹介しよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| 個人・グループ | 中級以上 | 国内 | メタ認知・社会的ストラテジー |
活動のねらい
外国人が母国について日本人から質問されることは意外に多いものである。
漠然と「あなたの国はどんな国ですか。」と聞かれることもあるだろうし,「食べ物について教えてください。」というようにテーマを絞って聞かれることもある。そんなときに役立つのがこのタスクである。
これは日本人との相互理解にも役立つし,自分の国を客観的に見るよい機会にもなる。また,日本の学校では最近外国人を講師に招いて外国の文化について学ぶ勉強が行われている。講師として依頼された時にも役立つタスクであるし,日本人との会話の話題にもなる。
タスク
- テーマを決める。(食文化,スポーツ,年中行事,家庭生活,学校生活,若者の文化,あるいは,いろいろな内容を盛り込んだ全般的な紹介でもよいです。)
- 対象(話す相手)を決め,相手に合わせた内容を考える。(大人,大学生,小中学生,ビジネスパースン,主婦,高齢者,など)
- 資料として使うものを考える。(写真,地図,実物,ビデオ,など)
- 相手の興味を引くような内容をわかりやすく説明できるように工夫する。
- 相手から出そうな質問と,それにどう答えるかも考えておく。
| テーマ | |
|---|---|
| 話の内容と流れ | |
| 予想される質問 | |
| 資料として使うもの, 準備するもの |
16. フリーマーケットに出店しよう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| グループ | 中級以上 | 国内 | メタ認知・社会的ストラテジー |
ねらい
フリーマーケットに出店するという共同作業を通じて,学習者どうしが協力しあうこと。また,来店する他者とのコミュニケーションをとることにより,自分の日本語能力を試し,実践的な日本語を使えるようにすること。
方法
- 出店する場所を探す。(ホームページや,地域の情報紙などを探すとよい)
- 予算は?(出店費用として,2000~5000円程度必要)
- どんなものを中心に売るか?
- 分担を決める。
- 当日の店番のローテーション
- 広報・宣伝係
- 会計係
- 出店予約をする。
- 電話の場合,先着順になる場合が多いので,注意。葉書は,抽選が多い。
- 売る物のリストを作る。
- 値段をつける。
- 売れやすい値段は?
- 新作や人気商品などは,高めに設定してみるのもよい。
- 小物のまとめ売りも,得策。
- どこまで値切れるか?
- ⇒紙に目立つ色で,値段を書く。
- 当日の準備。
- 必要なもののリストを作り,分担を決める。
レジャーシート,買い物袋,ペン,電卓,新聞紙 etc・・・ - 操作が難しい機器類には,説明書をつける。
- 必要なもののリストを作り,分担を決める。
- 広報・宣伝係はチラシを作って,学校や近所に張ったり,配ったりする。
- フリーマーケット当日
- 暇があれば,買い物もしよう。そこでのコミュニケーションも大事。
- 後日,反省会。以下のような表を作るとよい。
| 成功したこと | 失敗したこと |
|---|---|
| お客さんに母国の民芸品について聞かれ,話が弾んだ。 | お客さんに,品物について聞かれたがうまく答えられず,買ってもらえなかった。 |
| 隣のお店の人と仲良くなった。 | 強引な値引きに応じさせられてしまった。 |
| 客との値引き交渉がうまくいった。 | おつりを間違えて,怒られた。 |
17. 黒板かるた取り
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| クラス | 初級~ | 国内・海外 | 記憶・メタ認知ストラテジー |
目的
能動的に楽しく語彙の復習・定着を図る。
単語帳作りやノート整理の方法を考える。
活動内容
- 二グループに分かれ,黒板に今日習った単語を一人ずつ順番に書く。時間3分 (名詞,形容詞,動詞,文型など)
注意;後のかるた取りのために,ばらばらに書く。 - 書かれたものの答えあわせ。→正解の多いグループが勝ち。
- 黒板に書かれたもので黒板かるた取りをする。
- 読み手の言う単語を各グループひとりずつ出て交代に棒で差す。
- 早く差した人が多いグループの勝ち。
- 黒板の語彙をタスクシートに書く。
- タスクシートをきっかけに,効率的な単語帳作りや,ノート整理の方法を,学習者と考える。
- 担当者がクラスのメーリングに今日の学習記録,感想をUPする。
タスクシート例
| 名詞 | 動詞 | い形容詞 | な形容詞 | 文型・その他 |
|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
発展的活動
学習記録日誌を個人から,1. ML → 2. メルマガ → 3. HPに掲載 と発表の場を段階的に広げ,自然な形で語学学習が行なわれる環境を作る。
- クラスに学習日誌をMLに流す(クラスメート間の関わりが,学習ストラテジーにつながる)
- 不特定多数の読者対象のメルマガに今日の学習日誌をUPする。(読者が増えること)
- 不特定多数の読者対象HPに学習記録を整理,まとめてUPする。(読者が増えること)
18. 私がちょっとできること
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| クラス | 初級~ | 国内・海外 | メタ認知・社会的ストラテジー |
目的
自己・他者をモニターし,「自分やクラスメートができることを発見,共有」する。
教室という同じ空間を共有していても,クラスメートのことは,案外知らないもの。同様に,自分のことも明確に意識していないことが多い。言葉を使うことで,自分や他人を再発見できる活動は語学学習を楽しいものにする。
「ちょっと,できること」は,学習者が自然な形で,社会的ストラテジーやメタ認知ストラテジーを使う活動の一例である。
活動時期:「~てあげる ~もらう ~できる ~ていただけませんか」の学習後
活動手順
- シート:「あなたができる,ちょっとしたことをグループで話しながら書いてください。」
- 発表:(実際例)パソコンができる,韓国語ができる,キムチが作れる,水泳ができる,安い食べ物やさんを教えることができる,中国の遊びを教えることができる,韓国・中国の歴史を教えること,名所旧跡を案内することができる(韓国・中国)歌を歌ってあげられる,パンダの絵を描いてあげられる,巨人の選手の名前を教えてあげられる,サッカーの選手について教えてあげられる,…など出た。
- 交渉:発表を聞いて,してもらいたいことがあったら,交渉してみましょう。
- 発表:交渉経過と感想
(実際感想)小さなことでも,他人に喜ばれるのは嬉しい。自分は結構できることがあるのに気づいた。○○さんに韓国語を教えてもらうことができてうれしい。‥等 - まとめ:(記録係がMLで流す)
19. オリジナル日めくりカレンダー「これが日本語で言えますか?」を作ろう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| クラス | 初級~ | 国内 | 認知・社会的ストラテジー |
目的
毎日の生活でわからなかった表現を記録し,確認する習慣をつけさせる。
収集した日本語表現を「日めくりカレンダー」にまとめあげることにより「クラスの一年」を形にする。
「日めくりカレンダー」という身近にあっても見逃されがちなリソースに着目し,カレンダーという1年を通して使うものに係わることで1日1日を積み上げていくことの大切さを体感させる。
手作りの日めくりカレンダーを母国に持ち帰った生徒達は,毎日カレンダーをめくりながら日本での生活を思い出し日本語学習継続のきっかけになればと願う。
作業
日本の日めくりカレンダーについて実物を見せて説明する。
クラスで日本語表現をあつめて,翌年用のオリジナル日めくりカレンダー「これが日本語で言えますか?」を作り,自分の国にそれぞれもって帰る。
日本語表現の収集の仕方
既成の本などからとるのではなく,毎日の生活のなかで各自が理解できなかった表現,どう言っていいのか解らなかった表現をクラスに持ち帰り,クラスで話し合い,その情報を共有しながら「日本語表現」をクラス単位で収集していく。
収集の仕方はたとえば各自一冊のノートを用意し,個人で新しく覚えた単語,表現を毎日書き取ることを習慣にするとともに,クラスメートがクラスに提示した日本語表現も必要なものは自分のノートに書きとめていく。教師はクラスメートだけで解決できない日本語表現についてサポートし,クラスに持ち込まれた表現すべてをパソコンに入れておく。
日めくりカレンダーづくり
収集された日本語表現,各自でノートに書きとめた日本語表現から365の表現を選んで,日めくりカレンダーに編集する方法を話しあう。パソコンを有効利用する。
| 1月1日 | あけましておめでとうございます。 / A happy new year. 明日の問題: It snowed a lot yesterday, didn’t it? |
| 1月2日 | 昨日は雪がよくふりましたねえ。/ It snowed a lot yesterday, didn’t it? 明日の問題: Japanese cuisine is wonderful,but I don't like Natto very much. |
集められた日本語表現を日本の四季にあわせて分類し,年中行事,大学やクラスの行事などをうまく取り入れて編集できると良い。
表現は,「きれいな日本語」ではなく,「生きた日本語」を収集して,手作りの味が出せたほうがよい。
出来上がったオリジナルカレンダーは日本語部分についてはクラス全員同じで,英語がわからない学生は「明日の問題」の部分を自分で母国語にして持ち帰る。
次年度のクラスに1冊寄贈しても良い。
20. いっしょに作文を書こう
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| クラス | 留学生 | 国内 | 情意ストラテジー |
目的
留学生が日常感じている学生生活での違和感の解決する助けとする。
インタビューを通じてネットワークをつくる。
内容
- 協働作文
- インタビュー
活動
留学生が日常感じている学生生活の違和感を明確に意識し,言葉にすることで,留学生独自のものなのか,学生共有のものなのかを探るために作文を協働で書き,それをもとに一般学生にアンケートをとり結果をまとめ発表する。
タスク
- グループごとにトピック「学生生活で疑問に思うこと」を決める。
- 400字程度の作文を書く
- グループ内のディスカッションをする。
- 自分の作文と似ているところ,違うところを話し合う。
- 内容についてお互いに相談したいところを出し合う。
- 作文で直した方がいいところを話し合って作文を完成させる。
- 作文をもとにアンケート項目を作る。
- インタビューによるアンケートをとる
- インタビューの結果当初の思いがどう変化したかを各自まとめる。
- 今後のネットワークを継続的なものにするためにインタビューに応じてくれた学生も招待して結果をまとめたものを発表する。
評価
ポートフォリオ
- グループディスカッションのメモ・作文・アンケート案とまとめ
- 発表会の招待状・口頭発表
参考文献
- 池田玲子 2002 『「大学生のための表現法」における協働作文学習の試み』〈大学生のための表現方法〉水産大学
- 早稲田大学日本語研究教育センター 1999 『合本 留学生とともに考える「日本事情」』 早稲田大学日本語研究教育センター
21. 申し込み制テスト
| 参加者 | 対象者 | 場面 | ストラテジー |
|---|---|---|---|
| クラス | 初級~ | 国内 | メタ認知・社会的ストラテジー |
目的
*個人の自律学習と教室内での協働作業の合体
~monitoring learning progress 具現化の試み~
- 個人の自律学習
- 日常生活で周囲にアンテナをはりめぐらせ題材を拾って日本語にまとめる訓練を習慣化させる。
- 文集にのせたい作文を自分で選択,修正する過程で自分の習得過程をモニターできる。
- 教室場面
- 教室を「学習共同体」ととらえ,個々の学習成果を文集にまとめる協働作業を通じて,個々の生徒の 特性,責任感,達成感を引き出したい。 ~one for all, all for one~
- 教師のスキルアップ
- 個々の生徒の習得過程(関心事,取り組み方,上達度)をモニターすることにより,学習者主体の自律学習に向け適切なフィードバックの方法をさぐっていく。
- またこの作業を何年か繰り返すことにより,蓄積されたデータは貴重なポートフォリオをなり得るであろう。
手順
年度の初めに教師はクラスの生徒に対し,毎月1回申し込み制の作文テストを実施すると発表する。
申し込み制作文テストとは
与えられたテーマについて決められた時間内に作文を書くテストである。
教師は年度の初めに「テスト1. 」~「テスト8.」までの作文課題を一覧表にして出す(課題のレベルをコントロールすることで,すべてのレベルの学習者に対応可能)。
中級クラスの課題例
- テスト1. 5年後の自分
- テスト2. 日本にいる間に挑戦したいこと
- テスト3. 一番好きな日本人
- テスト4. 自分の国について紹介してください
- テスト5. 自分の趣味・特技について
- テスト6. 日本で生活する上で,困ったこと,不思議なこと
- テスト7. 日本のお勧めスポット
- テスト8. 最近のニュースから(身の回りのニュース,公のニュース共可)
生徒はテスト実施日の一週間前に,上記一覧表の中からその月に受けたいテストを申し込み,テスト当日は申し込んだテストの作文課題について書く。
メモや,資料を持ち込んでもいいが,必ず時間内で決められた用紙にそれぞれのテーマについて書かなければならない。テーマの範囲内で各自書きたいことを自由に書く。(たとえば「テスト3. 好きな日本人」について書く場合,歴史上の人物,有名人,身近にいる日本人など,選択に幅がある)
教師は,それぞれの「答案=作文」に目をとおし,適切なフィードバックをした後,生徒に返却。生徒は,返却されたテストを必要があれば修正してそれぞれがファイルしておく。
翌月,生徒は再びテスト1週間前までに受けるテストを選択し,申し込んでテストを受ける。
「教師のフィードバック → ファイル」これを毎月繰り返し,8ヶ月間で全員がテスト1. ~8. すべてのテストをうけることを義務付ける。
ファイルの最初に,下記のような表を書いた用紙をとじて,受け終わったテストの番号を好きな色で塗りつぶしていく。8ヶ月で表はすべて塗りつぶされる(どのテストから受けてもいいが,8ヶ月ですべてのテストをうけなくてはならない)。
| テスト1. | テスト2. | テスト3. | テスト4. |
| テスト5. | テスト6. | テスト7. | テスト8. |
2~3ヶ月すると申し込み制テストは習慣となり,生徒はそれぞれ次回どのテストを選んでどんなことを書こうかと思いをめぐらせ,題材を拾うために日常生活を注意深く観察したり,他の生徒との情報の交換(すでにどのテストを受けてどんなことについて書いたかなど)をはじめるようになる。
8ヶ月後には上記すべてのテストを全員が受け終わり,各自は8種の作文のファイルを持つ。
8ヶ月後
教師は,この作文テストをもとにクラスの記念文集を作ることを提案。
生徒は各自のファイルの8種の作文を読み返し,文集にのせたい作文を2テーマ自分で選び出す。(他の生徒に選んでもらってもよい。)
生徒は文集にのせる準備をはじめる。
ファイルされている作文をそのまま載せてもいいし,内容の書き足し,変更も可能(8ヶ月経過した時点で,文法知識,作文能力は向上していると思うので,同じテーマについても書き方が違ってくるはず)。
資料を添えたり,新たに取材に行くなども行い,それぞれ自分で選んだ2テーマについて文集にのせる作文を完成させる。
生徒主体で文集の編集作業にとりかかる。文集制作プロジェクトチームを発足させて作業を分担(表紙,挿絵,印刷など)しながら,まとめあげる。
アイディアいっぱいの文集をそれぞれの生徒がクラスの記念品として持ち帰る。
Brown, Kristine. 1999 Monitoring Learner Progress 翻訳
こちらのページから。
文献一覧
こちらのページから。
おわりに
ここで,英語学習に悩む早大生W君の話を紹介しよう。
彼は,高校時代から英語にはある程度自信があり,大学でも英語サークルに入っている。W君は,3年になり,学生生活にも慣れてきたので,英語力に磨きをかけようと,アメリカへの語学留学を志し,東海岸にある有名な大学付属にあるESL学校で行われる夏期集中コースへの入学を申し込んだ。7月になり,大学の授業も終わったので,留学へ期待を膨らませて渡航し,クラスに行ったところ,ほとんどが日本人だったという。
クラスの担当は,JETプログラムで日本に行ったことがあるトニー先生。授業はわかりやすく楽しいが,トニー先生,日本滞在中に覚えた日本語を使いたいのか,しきりに日本語で説明したがるが,いささか怪しい日本語でよくわからない。だが,当の本人は,バイリンガルの英語教師にでもなったようでご満悦な様子。休み時間も,日本人同士のネットワークが主なため,使用言語はどうしても日本語になってしまう。ヒスパニック系や韓国からの留学生もいるが,向こうも同じく母語でおしゃべりをしている。W君,生きた英語でも使いながら,一人でランチを食べに行こうとするが,クラスメートのK君に誘われ,近くにできたラーメンショップやすしバーに行き,日本語で注文する。一日の授業が終わり,寮に戻ると,これがまた日本人だらけ。時々カラオケに誘われて,J-ポップを歌いまくる。さらに,同室のT君,M君が,よくインターネットカフェに行くので,一緒に着いて行き,Yahoo Japanで面白そうなサイト見学をする。気がつけば,日本語でメールを打っている自分に気がつくW君だった。
そんなW君は,ふと考える。アメリカに来て,本当に英語力がアップしたのかなぁ……。
あなたの近くにも,「W君」はいませんか。日本に来れば日本語が自然に上達する。そんな迷信に惑わされることなく,自律学習能力をつけるにはどうすればいいのでしょうか。自らの言語問題をモニターし,そうした問題をどのように取り除くべきか,さらには,教師の管理から離れ,自律していくための処方箋を考える必要があります。受身の学習では,習得に結びつきません。自らが,いかに能動的に習得に働きかけるか……。
本書が,そうした問題を考えるきっかけになれば,作成者全員の初期の目的は達成されたことになるでしょう。
宮崎里司(早稲田大学大学院日本語教育研究科)
早稲田大学日本語研究教育センター
2002年度 日本語・日本語教育研究講座
「言語学習ストラテジー概論」受講生(五十音順)
- 伊東陽子
- 木野緑
- 金恵娥
- 久保田洵
- 近藤扶美
- 鈴木真理子
- 坪井千穂
- 橋本明子
- 濱田奈央
- 早野香
- 本柳とみ子
- 矢崎弥生子
- 米田京子